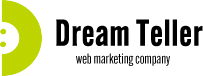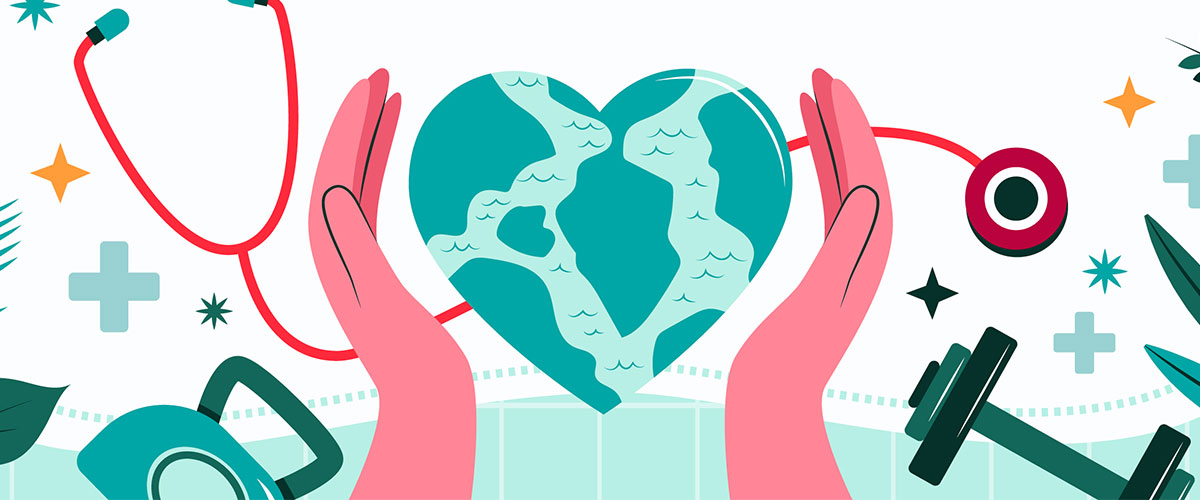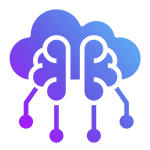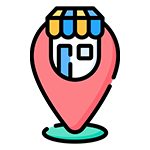WELQ問題から学ぶ:検索評価が厳しいジャンルとオウンドメディアの正しい向き合い方
はじめに:テーマ選びを間違えると、SEOでは致命傷に
オウンドメディアは、企業や個人が情報発信を通じて見込み顧客との接点を築く有力な手段です。
しかしテーマ選定を誤ると、検索エンジンからの評価が極端に低くなったり、最悪の場合はインデックス削除という事態も起こり得ます。
この記事では、2016年に大きな話題となった「WELQ問題」から始まり、今日のGoogle検索評価の厳格化までを踏まえながら、オウンドメディアで扱う際に注意すべきジャンルと、その正しい対処法を解説します。
WELQ問題とは?SEO業界に与えた影響
WELQ(ウェルク)はDeNAが運営していた医療系キュレーションメディアで、2016年に専門性のない不正確な医療記事を大量掲載していたことが問題視されました。
「肩こりは幽霊のせい」「◯◯を飲めばがんが治る」といった内容がSEO的に上位表示されていたため、大きな社会的批判を浴び、Googleもアルゴリズムを大幅に見直す契機となりました。
この事件をきっかけに、Googleは信頼性・専門性・権威性を重視する評価軸(E-A-T→E-E-A-T)を強化し、とくに「人の命やお金に関わるジャンル」への評価基準を厳格化しました。
YMYLとE-E-A-T:評価が厳しいジャンルとは?
Googleは、「Your Money or Your Life(YMYL)」と呼ばれるジャンルに対して、特に高い品質・信頼性を求めます。YMYLに該当するのは、以下のようなテーマです。
- 医療・健康(病気、治療、サプリ等)
- 法律・労働・雇用に関する情報
- 金融(投資、副業、ローン、仮想通貨など)
- 安全・公共の政策に関わる話題
- 子育て、教育、人生の重大な意思決定に関わる情報
このような領域では、「体験談」や「独自解釈」だけでは通用しません。
専門家の監修、一次情報の引用、発信者の実在性などが、検索上位に表示されるための前提条件となります。
特に注意すべきジャンルとリスクの具体例
健康・医療ジャンル
健康法、栄養、サプリメント、病気の対処法などは、個人の体験談や曖昧な出典情報ではほぼ評価されません。
誤情報の拡散による社会的影響が大きいため、医師や薬剤師など国家資格保有者の監修がない記事は上位表示が難しくなっています。
金融・投資・副業ジャンル
お金に関わる内容(クレジットカード、ローン、仮想通貨、副業紹介など)は、収益性が高い反面、規制も厳しい領域です。
特に「◯ヶ月で〇〇万円稼げる」系の表現は、根拠が曖昧だとGoogleのペナルティ対象になる可能性があります。
法律・労務・就労・離婚など
弁護士や社会保険労務士などの専門家による記述・監修が求められる領域です。
法律の誤解を招く記事はユーザーに深刻な損害を与えるリスクがあるため、評価は非常に厳しくなっています。
検索評価を落とさないための“向き合い方”と対処法
- 専門家の監修・寄稿を必ず明示
監修者の名前・資格・所属などを記事内や監修欄に明記し、信頼性を担保しましょう。 - 一次情報や公的資料の引用を徹底
曖昧な噂話ではなく、厚労省・消費者庁・国税庁などの公式情報に基づいて構成すること。 - 執筆者情報・運営者情報をしっかり記載
記事単位だけでなく、メディア自体の運営主体が“顔の見える状態”になっていることが重要です。 - ユーザー体験ベースの記事は「体験談」と明記
「あくまで個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません」という表現を添えるのがベター。 - 無理にYMYLジャンルを狙わない戦略も有効
本業の実績や事例をベースに、「サービス紹介」や「ノウハウ共有」の形で構成する方法も安全です。
要するに、「誰が」「何を」「どう伝えるか」が検索評価に直結する時代です。
まとめ:信頼性こそが“コンテンツSEO”の本質
WELQ問題は「検索エンジンの抜け道」を使った短期的な成果が、どれだけ危険かを象徴した事件でした。
現在のSEOは小手先ではなく、ユーザーにとって有益で、信頼できる情報を提供することが前提です。
YMYLジャンルに限らず、どの分野でもGoogleは“発信者の信用”を重視しています。
オウンドメディアを育てるなら、「正しいテーマ選び」と「誠実な運営方針」から始めましょう。