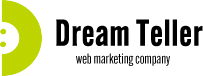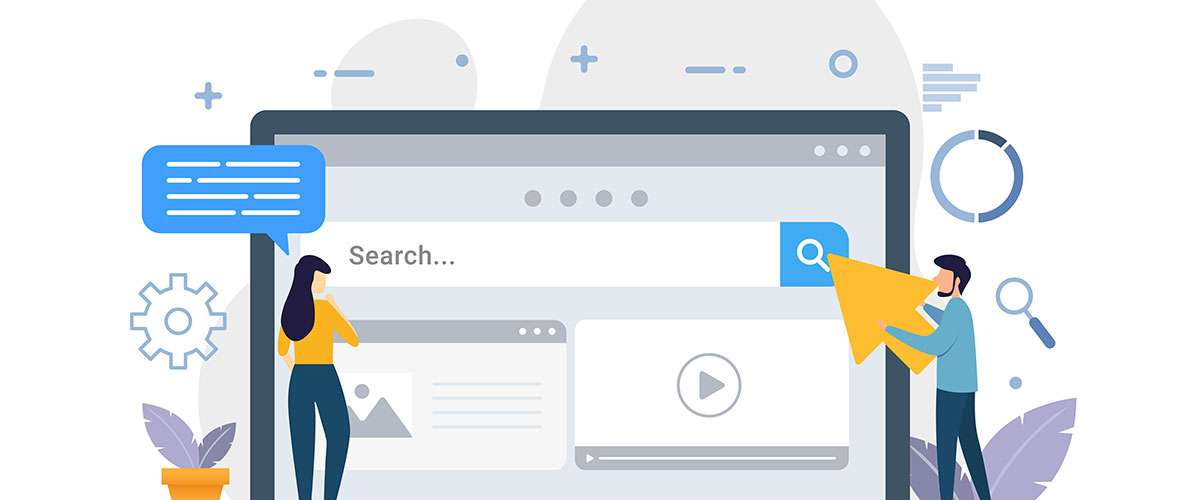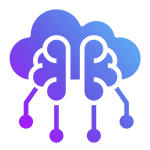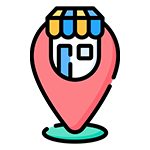全てお任せは危険?初めてのホームページ制作で後悔しないための基礎知識
「HPの事はよく分からないのでお任せします」は危険?
実際の制作現場で「ホームページの事は全然わからないので、デザインやページ構成などお任せします。」というお客様は結構います。
僕はこの言葉を聞くと、信頼してもらえている!と喜ぶのではなく、「自分の会社の事なのに投げやりだな」「前のめりじゃないな」と残念に感じてしまいます。
もし悪徳な業者や、作って終わり系の業者だった場合、こういう事を言うと、足元を見られかねないですし、手抜きされるリスクさえあります。
丸投げし過ぎて残念な結果になって欲しくない、さらには、もっとホームページに取り組む意識を高めて欲しい!という想いから今回の記事を書かせて頂きました。
ホームページは「会社の顔」──だけど、知らないままでいいの?
ホームページは、お客様や取引先が最初に出会うあなたの「顔」です。
初対面の印象がその後の関係を左右するように、ホームページの第一印象はビジネスの信用や売上に直結する可能性があります。
にもかかわらず、「よく分からないのでお任せします」という姿勢で作ってしまうと、表面的にはキレイでも成果に結びつかない「自己満サイト」が出来上がってしまうことがあります。
ホームページは単なるデジタル名刺ではなく、集客・ブランディング・採用・信頼構築など、多機能な営業ツールです。
制作段階で正しい設計と方向性を持たずに作ってしまうと、その後の修正に時間も費用もかかってしまいます。
「お任せしたのに結果が出ない…」と後悔しないためにも、最低限の知識を持っておくことは必須なのです。
なぜ「全部お任せ」が危険なのか?
制作会社はデザインやコーディングのプロではあっても、あなたの事業内容や顧客像については当然ながら素人です。
誰に・何を・どう届けるのかという本質部分を明確に伝えないまま制作を進めると、結果的に「誰にも響かない」サイトになるリスクがあります。
特にBtoBサービスや専門性の高い業種では、「業者に全部任せればなんとかなるだろう」と思っていると、業種の特性や顧客の悩みが全く反映されないページになってしまいます。
制作パートナーとは“共同制作”の意識を持って進めることが、成功の鍵になります。
最低限押さえておきたい5つのチェックポイント
- 自社の強みやサービスを言語化できているか:競合と比べたときの優位性は? 他社にはない特徴は?
- 誰に向けて作るサイトか(ターゲットの明確化):年齢、性別、悩み、ライフスタイルまで想定できているか?
- 更新・運用は誰が担当するのか決まっているか:情報が古いと信頼性が下がるため、運用体制は重要です。
- 将来的にどのように活用していきたいか:集客・採用・信頼構築など、目的に応じた設計が必要です。
- 業者に任せる範囲と、自分たちがやるべき範囲の整理:写真提供、文章作成、運用方針の決定など、分担を明確に。
これらはすべて「事前準備」の段階で整えるべきことです。準備不足のまま制作を進めると、方向性がブレて、あとから「こんなはずじゃなかった…」と感じることになりかねません。
制作業者選びは「制作物」だけじゃなく「対応姿勢」も見よう
ホームページ制作会社は多数ありますが、見積額やデザイン実績だけで選ぶと失敗することもあります。
運用フェーズでの対応力・柔軟性・連絡の取りやすさなど、プロジェクトを一緒に進める上での信頼感がとても重要です。
特に、公開後のちょっとした修正や相談に迅速に対応してくれるか、アクセス解析を元に改善提案をくれるか──といった姿勢は、“作っただけ”では終わらない体制づくりに大きな影響を与えます。
「育てるホームページ」という考え方
ホームページは「完成したら終わり」ではありません。
公開後にどれだけ改善・更新を繰り返せるかによって、集客力・信頼力・CV率は大きく変わります。
例えば、アクセス解析から「よく見られているページ」「離脱されやすいページ」を特定し、レイアウトや文言を見直す。FAQを追加してユーザーの不安を解消する。新商品・新サービスが出るたびに記事を増やしてSEOを強化する。
こうした積み重ねが、ホームページを「静的な名刺」から「生きた営業ツール」へと進化させます。
まとめ:お任せしつつ「丸投げしない」姿勢が成功への近道
ホームページ制作において、「任せるべきところ」と「自分たちが考えるべきところ」の線引きを明確にすることが重要です。
制作業者はパートナーであり、一緒に成果を出すチームの一員という意識で関わることが理想です。
専門的な部分はプロに任せるとしても、事業への想い・お客様の声・現場の温度感などは、現場にしか出せない価値ある情報です。
それを制作会社にしっかり共有しながら、共に作り上げていくことで、成果につながるホームページが生まれます。
「とりあえず作ったけど、まったく反響がない…」とならないよう、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。