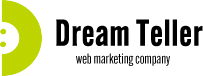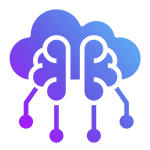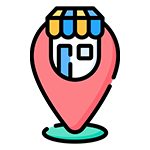Z世代は“家も車も買わない”時代へ|5年後、10年後を見据えて今からできる事業転換のヒント
はじめに|常識が変わる時代、今こそ構造的変化に目を向ける
「家を買って一人前」「車を持って自由を手に入れる」——そんな価値観は、もはや過去のものになりつつあります。
Z世代、そしてこれから社会に出てくるα世代は、“所有”ではなく“体験”と“柔軟性”を重視する世代です。
持ち家率の低下、車離れ、所有しない文化、そして少子化…。これらの要素が複合的に絡み合い、従来型のビジネスモデルに根本的な見直しを迫っています。
本記事では、今後厳しくなる業界の特徴と、そこから導かれる「今からできる事業転換のヒント」を全5回に分けて解説します。
Z世代・α世代の価値観変化|「持たない」を前提に育つ世代
1997年以降生まれのZ世代、そして2013年以降のα世代。彼らは次のような環境で育ってきました:
- ・親世代の“住宅ローン疲れ”を間近で見ている
- ・サブスク、シェアリング、レンタルが生活に根付いている
- ・終身雇用が崩れ、ライフプランの流動性が高い
- ・SNSの影響で「見せ方」「体験」「軽やかさ」が重視される
こうした背景から、家や車といった大型消費に対しては「縛られたくない」「柔軟に生きたい」という意識が強くなっています。
データから見る“持たない時代”の到来
総務省統計局の調査でも、30代以下の持ち家率はここ10年で下がり続けています。
また、若年層の普通自動車保有率も年々低下しており、「免許は持つが、買わない」という選択が主流になりつつあります。
同時に、「引っ越し前提の家具サブスク」「車はカーシェアだけでOK」「家は買わず賃貸で自由に」など、“固定資産を持たない暮らし”がライフスタイルとして定着しつつあるのです。
この変化が直撃する業界とは?
この価値観シフトが、今後5〜10年で直撃する業種は少なくありません。特に以下のような業界は構造的な市場縮小に直面すると考えられます:
- ・戸建て向けの外壁塗装/屋根工事/エクステリア施工
- ・カーポート/ガレージ設置業者
- ・太陽光パネルの個人住宅向け販売会社
- ・家具/インテリアの大型販売店(持ち家前提の商品群)
- ・新築注文住宅/高額リノベーション業者
これらはすべて「持ち家を買う」「家にお金をかける」ことが前提のビジネスです。
若者の所有志向が減退すれば、市場そのものが縮小するのは避けられません。
少子化×価値観変化で打撃を受けるその他の業種
家・車だけでなく、若者が“買わない・持たない”前提で生きる社会では、“家庭を持たない層”がボリュームゾーンになるため、以下の業界も苦境に立たされます。
- ・仏壇・墓石・葬儀業(家制度・供養文化の衰退)
- ・ベビー・キッズ用品(出生数の減少)
- ・結婚式場・ブライダル関連(未婚・挙式しない層の増加)
- ・習い事(書道・珠算など伝統系、児童数の激減)
- ・地方型の学習塾・予備校(都市集中+少子化のWパンチ)
特に「地域密着・子ども中心」で成り立っていた業態は、人口構造の変化により商圏そのものが崩壊する可能性があります。
高齢者依存・儀式型ビジネスの構造リスク
高齢者を主顧客とする業種も要注意です。
その理由は2つあります。
- ①顧客が減る:2030年以降は高齢者人口も減少に転じます。
- ②需要の形が変わる:簡素化・合理化・ネット対応が求められる。
たとえば「直葬」や「海洋散骨」が主流化し、「仏壇や墓石を買わない」「自宅に何も残さない」が新常識になりつつあります。
“儀式文化に依存した業態”は、リブランディングしない限り縮小不可避です。
地方×固定店舗型ビジネスの衰退
都市集中・若者の移動性重視の影響で、地方・郊外の固定店舗型ビジネスも生き残りが難しくなってきています。
- ・地元商店/個人スーパー(ネット購入への移行)
- ・地方書店・CDショップ(サブスク化)
- ・町の不動産仲介(アプリ完結の時代)
- ・地場の印刷会社・販促物制作(紙からWebへ)
若者がいなくなる・固定資産を持たない・外に出ない時代に、「来店前提」のビジネスは限界を迎えます。
まとめ:縮小確定の業界は「顧客構造×価値観」のズレから見える
今後厳しくなる業界には共通点があります。それは:
- ・家族・持ち家・車など「固定された所有」を前提にしている
- ・子どもや高齢者など「人数が減る層」に依存している
- ・“来店してもらう”など、時代の行動様式に合わない
今のやり方に固執すればするほど、数年後の現実に苦しむことになります。
では、どうする?今からできる事業転換の方向性
「じゃあ、これから何をすればいいのか?」——答えは単純ではありません。
しかし、成功している企業には共通する“転換の型”があります。ここでは、そのヒントとなる方向性を整理します。
① BtoCからBtoBへ|顧客の構造を変える
一般個人を対象とした事業が厳しい場合、法人や業者向けのサービス提供へ転換するのが有効です。
- ・外壁塗装 → 管理会社・オーナー・建築会社と組む
- ・リフォーム → 介護事業者や福祉施設との提携へ
- ・インテリア販売 → ホテル・オフィス向けの空間提案業へ進化
少子化が止まらない以上、「一人一人に売る」だけでは限界が来ます。企業や組織を顧客にする仕組みへ軸足を移すことが現実的です。
② 所有から利用へ|“モノ売り”から“サービス提供”へ
車・住宅・家具・服など、従来は「買ってもらう」ことがゴールだった商品でも、「使わせる」「選ばせる」ことで収益化する方法があります。
- ・家具販売 → 家具付き賃貸との提携/月額レンタルサービス
- ・車販売 → カーシェアリング運営/法人契約プラン
- ・高額家電 → 法人リースやサブスク提供への切り替え
所有を前提としない若年層が増える中、“一括で売る”よりも“継続的に使わせる”モデルへのシフトが必要です。
③ 地方から都市/オフラインからオンラインへ
人が減っていく地方や、商圏縮小が見込まれる立地で事業をしている場合、市場を変える勇気が必要になります。
- ・店舗型 → EC/オンライン相談/予約制訪問型へ
- ・地元密着 → 都市圏の法人との取引・業務提携へ
- ・紙販促 → SNS運用代行/LINE公式アカウント支援へ
「いつか人が戻ってくるかも」という期待ではなく、“市場のある場所”に自ら動く発想が求められています。
④ 一回売って終わり → 継続で収益を生む仕組みへ
かつての主流は「一度売って終わり」でした。
しかし人口減少時代には、新規顧客の獲得より“継続課金型”のビジネスモデルが安定します。
- ・外壁塗装 → 定期点検付きメンテナンスサブスク
- ・リフォーム → 保守・アップグレードの月額サービス
- ・習い事 → オンライン講座+サポート付きの月会費型に
高齢化社会では“継続して安心してもらう”こと自体が価値です。売って終わりではなく、関係を持ち続ける設計が生き残りのカギになります。
⑤ サービス業は「副業・兼業・短期」で売る方向性を
フルタイム雇用が減る中、Z世代は副業・短期集中・スポット労働を好みます。
そのため、サービス提供側も「一括の請負契約」より、「小口・成果連動型・選べる単位」で展開すべきです。
- ・撮影 → SNS投稿1本単位でのパッケージ化
- ・デザイン → テンプレ提供+アレンジサポート
- ・塾講師/講座 → 単発受講・成果保証プランへ
Z世代は「選べる自由」があることを強く好みます。
“全部付きで高額”ではなく“必要なだけ選べる安価”が、今後の基本戦略になります。
⑥ SNS・検索ではなく“推薦される”会社へ
Z世代は検索しません。SNSを使うと言っても、「調べる」のではなく「流れてきたものの中から選ぶ」のです。
つまり、“発信者に選ばれる存在”になることが重要になります。
- ・お客様の体験談をコンテンツ化
- ・TikTokやYouTubeの発信者に商品提供
- ・口コミやリールで“選ばれる理由”を言語化
どんなに良いサービスでも「知られなければ選ばれない」時代です。“検索される努力”ではなく“推薦される努力”へのシフトが不可欠です。
⑦ 顧客と「共創」する企業文化へ
Z世代以降は、ただ“与えられる”よりも、“一緒に作る”という体験に価値を見出します。
そのため、事業者側も顧客と一緒に価値を作る「共創型」の姿勢が求められます。
- ・社員食堂のメニューに社員が提案
- ・制服デザインを社内アンケートで決定
- ・新商品や新サービスの意見募集から実装まで公開
「あなたの声が会社を変えた」「自分のアイデアが形になった」という体験が、定着率・ファン化・口コミ拡散すべてに効果を発揮します。
まとめ|“変化を受け入れる企業”だけが生き残る
持ち家・車・終身雇用——そうした“かつての常識”が崩れる中、ビジネスの基盤そのものが再定義されようとしています。
「今のやり方を守る」のではなく、「今のやり方を“疑い”、変えていく」ことができる企業こそが、5年後・10年後に強い存在でいられます。
本記事で紹介したような市場構造の変化×顧客の価値観変化をしっかり受け止め、今から段階的に転換・改善を始めることが、未来への備えです。
そして、どんな時代であっても「顧客との関係性」を軸に再構築することが、最強の生存戦略になるのです。