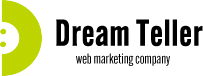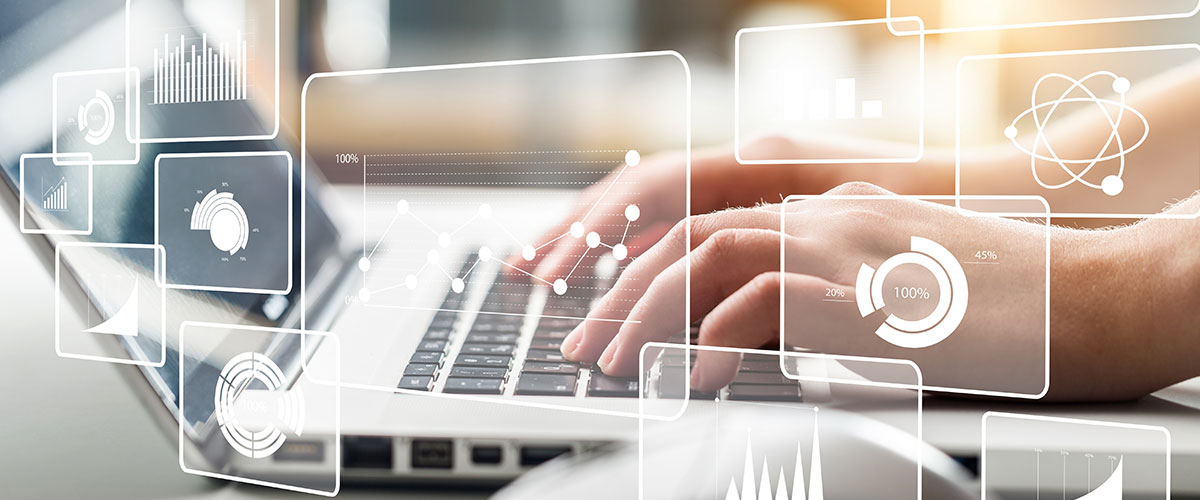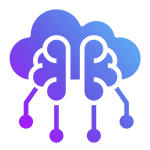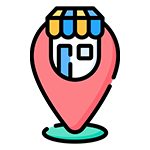【制作現場の本音】WEB担当者に求められる7つの姿勢:ホームページで成果を出すために
はじめに:WEB担当者の「姿勢」が成果を左右する
これまで15年以上、ホームページ制作会社として数百社と関わり、数多くのプロジェクトを進めてきました。
特にWEBディレクターとして感じているのが、「担当者のスタンス一つで、プロジェクトの成否は大きく変わる」ということです。
経営者や決裁者との直接のやり取りでは、意思決定が早く、ゴールも明確なため、スムーズに進むことが多い一方で、 中間に立つ「WEB担当者」の存在が、プロジェクトを前に進める鍵にも、逆にストップ要因にもなります。
本記事では、実務の現場から見えてきた「成果を出すWEB担当者に共通する7つの姿勢」をご紹介します。
担当者として現場に立つ方はもちろん、経営者の方にも“任せ方の指針”として参考になれば幸いです。
1. 「決まっていないこと」をそのまま伝えない
制作会社とのやり取りで一番困るのが、「とりあえず話だけ伝える」パターンです。
決まっていない状態で曖昧なまま情報を渡されると、設計も提案も組み立てようがありません。
例:「たぶんこの辺を強調したいって言ってました」「会社の方針はまだ調整中です」など。
担当者がプロジェクトの“ブリッジ”である以上、「判断がつかないことは、判断の期限・誰が決めるか」まで明確にして伝える姿勢が大切です。
2. 「自社の強み」を言語化できるようにしておく
ホームページは“何を伝えるか”が全てです。にもかかわらず、自社の強みや独自性がWEB担当者の口から出てこないケースも珍しくありません。
「詳しくは社長に聞いてください」「営業部が一番わかってます」といった姿勢では、成果を出すページ設計は困難です。
担当者には、「競合との違い」や「選ばれる理由」を最低限でも把握し、“外部に伝える言葉”で話せる状態を目指してほしいのです。
3. 判断の遅れが“コスト”になることを意識する
デザインや構成に対するフィードバックが遅れると、それだけでスケジュールは後ろ倒しになります。
特に修正指示のたびに「社内確認に時間がかかる」というケースでは、制作会社側の稼働も増え、コストにも直結します。
担当者には「迅速な一次判断」または「誰がいつ判断するかの明確化」が求められます。
“決めることを決める”のも担当者の重要な役割です。
4. 「自社のゴール」を制作会社に丸投げしない
「集客したい」「問い合わせを増やしたい」という抽象的な目標はよく聞きますが、
具体的に「どんなターゲットに」「どのような行動を起こしてほしいのか」まで落とし込めている担当者は多くありません。
制作会社は“形にするプロ”ではありますが、「何を達成したいか」という方針は、クライアント側で定めるべきものです。
制作を「外注」ではなく「共創」と捉え、目的共有からスタートする姿勢が、良い結果につながります。
5. 社内に“巻き込む力”を持つ
WEB担当者の最大の役割のひとつが「社内調整」です。
情報提供を各部署に依頼したり、役員の確認を取ったりと、制作を前に進めるための潤滑油的な働きが必要です。
担当者が“自分の業務だけ”に集中してしまうと、制作側からは「何も決まらない」「誰も協力してくれない」状態に見えます。
社内の意見を集約し、制作会社に渡す情報を整理する力が、WEB担当者にとって極めて重要です。
6. デザインや表現の「好き・嫌い」に引っ張られすぎない
担当者の主観だけで「この色が嫌い」「なんとなく古く感じる」といった判断を繰り返すと、
ターゲットユーザーにとっての“伝わるサイト”からどんどんズレていってしまいます。
制作物に対する感想は大切ですが、「誰に、何を、どう伝えるか」の軸に立った判断が求められます。
感覚的な意見だけでなく、「根拠のある改善提案」を心がけることで、サイトの質も上がります。
7. 完成後も「運用の当事者」である意識を持つ
サイトは作って終わりではなく、そこからがスタートです。
コンテンツの更新、アクセス解析、ユーザーの反応チェックなど、運用フェーズでの担当者の関わり方が、サイトの価値を決定づけます。
特にSEOやCV改善に関しては、継続的に改善PDCAを回せるかどうかが大きな差になります。
担当者が「育てる意識」を持つことで、ホームページは“成果を生む資産”へと進化していきます。
まとめ:担当者はプロジェクト成功のキーパーソン
制作会社にとって、WEB担当者は「クライアントの代表」ともいえる存在です。
だからこそ、その姿勢や判断力がプロジェクト全体に影響を及ぼします。
今回紹介した7つの姿勢を意識することで、制作会社との連携がスムーズになり、結果として会社にとって価値あるホームページが完成します。
「良い担当者がいる会社は、やっぱり成果が出る」
これは、制作現場にいる者として何度も感じてきた事実です。
自社のWEBを“投資価値ある媒体”に育てるために、まずは担当者自身の在り方から見直してみてはいかがでしょうか。